「これはまた……ひどいな」
その物体を目にしたとき、オスカーが口にした言葉はそれしかなかった。
主星宙域に正体不明の物体が近づいてくるのを王立研究院が察知したのは、丁度オ
スカーが辺境惑星調査から帰還した直後のことだった。女王に報告に行く前にエルン
ストと鉢合わせたオスカーは、慌ただしく前を通りすぎようとする堅物主任の腕を掴
み、ことの詳細を説明させたのである。
「……謎の物体?」
「いえ、捕獲した現段階ではそれが何なのか、解明済みです」
無駄を一切排除したエルンストの報告と渡された書類の何枚かに目を通しながら、
オスカーは歩を緩めることはしない。まっすぐに目的の研究室に向かう彼の歩幅に辛
うじて合わせながら、エルンストもオスカーの隣に並んでいた。
王立研究院の地下に設置されている研究室は、余計なものが一切ない整然とした白
い空間だった。重々しい分厚い防護扉を開けて中に踏み入ると、更に奥に前面硝子張
りの部屋が現れる。オスカーとエルンストのいる手前のこの部屋は、モニター機器を
びっしりと詰めこんだ部屋で、硝子張りの部屋は研究対象物を安置する部屋となって
いる。
エルンストが手前の部屋に戻り、モニター機器を操作した。薄暗かった室内に白い
閃光が走り、周囲を明るく照らす。硝子越しに見やったその渦中の物体を瞳に映し
て、オスカーは思わず息を飲んだ。
「これはまた……ひどいな」
楕円形の物体は、焼け爛れた皮膚のような赤茶けた表面を見せている。オスカーは
それが宇宙船に常設されている救命ポットだと分かったが、一見しただけではそれと
は分からないほど醜く様相を変えていた。
オスカーは扉に手をかける。エルンストが何も言わないところをみると、当座の安
全は保証されているようだった。エルンストはモニターの画面を覗き込み、異常がな
いかどうかをチェックしていた。
オスカーは念の為扉を開け放したまま、その物体に近づく。救命ポットの継ぎ目は
すでに爛れた表層部分のお陰で、判別が出来ない。
「中に生命体の反応は?」
「微弱ですが、存在します。ですが……」
「何処にレーザーカッターを入れればいいのか分からない、ということか……」
苦く呟くオスカーに、エルンストはうなだれるようにして頷いた。
中の生命体がどのような形をしているのか、またこのポットの中でどの部分に位置
しているのかが分からなければ、ポットを解体するためのレーザーカッターを入れる
ことは極めて難しい。表層部分ではなく、下手をすれば中の生命体までもを両断しか
ねないのだ。
「陛下にご連絡を。指示を仰ぐのがいいだろう」
「はい。すぐに」
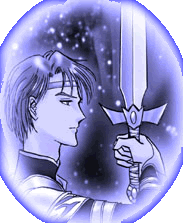 エルンストが頷いてモニタールームから出て行こうとする。
エルンストが頷いてモニタールームから出て行こうとする。その気配を背中で感じながらオスカーは何気なくポットの
表層部分に指を触れさせた。
ざらついた指触り――その固さを実感した直後、焼けつく
ような熱がオスカーに襲いかかってきた。
(炎!?)
赤、ではない。純粋な高熱のために通常目にしない色は、
オスカーの瞳と同じ色だった。ポットから灼熱の炎が襲い
かかってくる。
「――オスカーさま!!」
異常事態に気付いたエルンストが、こちらへ走り寄って来ようとする。オスカーは
炎を片腕で防ぎながらも舌打ちをし、扉のロックに拳を叩きつけた。
薄い硝子が弾け飛び、オスカーの拳が血に染まる。エルンストが辿り着くより早
く、その部屋の扉は閉じられ、あまつさえ施錠された。エルンストが血相を変えて扉
を叩く。
「オスカーさま!! ここを開けて下さい!!」
「それよりも先に女王陛下へご報告だ。これ以上被害が起きないように、ここは食い
止める」
「お一人で無理です……まだ何も分かってはいませんよ!」
エルンストの叫びに、オスカーはいつもの、少し皮肉げで余裕のある微笑を浮かべ
た。
「いや、見れば分かるさ。……泣いているのは、こいつだな……」
「オスカーさま!!」
「陛下に、こちらは大丈夫だと確かにお伝えしろよ?」
アンジェリークはふと何かを見たような気がして、顔を上げた。
重厚なデスクの上にはロザリアが手ずから運んできた決済待ちの書類が山と積ま
れ、アンジェリークの印章がその身に押しつけられるのを待っている。羽根ペンを動
かし、印章を押すアンジェリークの目の前では優秀な女王補佐官が立ち、アンジェ
リークの決済が必要なものと守護聖たちで対応できるものと、書類を選別していた。
アンジェリークの仕草に気付いたロザリアが、いぶかしげに彼女を見やる。
「陛下。どうかなさいまして?」
「今……炎が見えなかった?」
アンジェリークの問いかけにロザリアはわずかに戸惑ったように首を振った。
「いいえ……お間違えでは? 確かにオスカーは調査より帰還しておりますが……」
「ううん、オスカーの炎じゃないの。何て言うのかな……なんか、もっと……」
アンジェリークがうまく自分の感じたことを表現できず、唇を噛み締める。その直
後、執務室の扉がノックもなく激しく開け放たれた。
ロザリアが素早く立ち上がり、アンジェリークの前に身を滑り込ませる。しかし現
れたエルンストの姿を認めると、ほっと安堵したのもつかの間彼のいつにない表情の
厳しさにロザリアの視線も引き締められる。
ロザリアの背中から、アンジェリークが顔を出した。
「陛下……至急お話したいことが……!」
「落ち着いて、エルンスト。私はちゃんと聞いているわ。何があったの?」
エルンストは一度大きく深呼吸して息を整える。
「先ほど収容した救命ポットなのですが……突然何の前触れもなく火を放って、大変
危険な状態です」
「……中の生命反応はどうなってますか」
「微弱ながら反応は続いております。ですが、その炎の部屋にオスカーさまがお一人
で残っているのです!」
「――なんですって!?」
声を上げたのはアンジェリークではなくロザリアだった。アンジェリークは大きく
目を見張ったまま、息を詰めている。
アンジェリークは辛うじて倒れることを抑え込み、渇いた声を押し出した。
「それで、オスカーは何と?」
「陛下に……陛下にこちらは大丈夫だとお伝えしろと……」
(大丈夫)
アンジェリークはすとん、と心に滑り込んだオスカーの伝言にゆっくりと頷いた。
先ほどの動揺が嘘のように引いて、変わりに力強いものが生まれてくる。
「オスカーは、大丈夫だって言ったのね?」
「は、はい。これ以上被害が出ないようにここは食い止めると」
「陛下」
ロザリアがアンジェリークに指示を仰ぐ。アンジェリークは満面の笑みを浮かべて
答えた。
「オスカーは私に嘘をついたことは一度もないわ。オスカーが大丈夫だって言ったら
きっと大丈夫なのよ!」
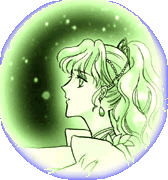 確信を込めて強く言うアンジェリークに、エルンストは唖然と
確信を込めて強く言うアンジェリークに、エルンストは唖然とする。多少この手のことに関して免疫のあるロザリアは、額を
指先で抑えながらエルンストに向き直った。
「そういうことですの。多分、陛下もそう仰る以上、大丈夫だと
思われますわ」
「だから私たちは私たちの出来ることをしましょう」
アンジェリークの笑顔が、毅然としたものへとゆっくりと変化
していく。それは幼さを滑り落し迷いを脱ぎ捨て、慈愛と神聖を
含んだものへと。
「エルンスト、消火活動を指示して下さい。私はサクリアを使って、中の生命体に
呼びかけてみます」
まるで陽炎のように揺らめく蒼い炎は一見すると夢のように美しい乱舞を披露して
いる。だがオスカーの肌には確かな灼熱感が叩きつけられ、マントの端は焼け焦げて
いた。不思議なのはこれだけ強烈な炎なのにも関わらず、熱がひどいだけで焼ける気
配がないということだ。
(だがあまり喜んでばかりもいられないな……このままだと蒸し焼きになる)
オスカーの執務服は絶え間なく噴き出す汗によって、ぐっしょりと濡れている。額
から滑り落ちた汗が精悍な頬を伝って、オスカーは乱暴にそれを袖口で拭った。
意を決して、救命ポットに近づく。炎が更に強くなり、熱風に圧されてオスカーの
踵が揺らいだ。
《アツイ・ノ》
オスカーは唇を噛み締める。全身に襲いかかってくる炎の合間に確かに見え隠れす
る、何らかの『思考』が――肌に突き刺さってくる。
それは、死への恐怖を目の当たりにした、血色の叫び。
《フネガ・エンジョウシ・テ。ワタシヒトリ・キリ。アツイ・ココハ》
「……そんなことを言いたいのか?」
オスカーは手を伸ばす。救命ポットの表層に掌が触れる。直後、強烈な灼熱感が肌
を焼いたが、オスカーの表情から不敵な笑みが消えることはなかった。
「違うだろう? お前が言いたいのはもっと別のことじゃないのか?」
《ワタシ・ハ》
オスカーはふ……っと瞳の威力を弱める。柔らかく微笑んで、今掌で触れている鉄
の下に在る命に囁きかける。
「何を、俺に言いたい?」
一瞬の間があった。やがて炎が一際大きく広がる。
《タスケ・テ》
光の羽根が、突如として現れた。それは救命ポットとオスカーを包み込み、燐光を
放つ。溢れる光は空間を一瞬にして満たし、それだけでは足らず周囲に広がってい
く。
女王のサクリア。オスカーは小さく笑った。
何もしていないのに、救命ポットのハッチがばくんっと開いた。そこから保護液が
流れ出て床に広がり、オスカーの足元を濡らす。
溢れる光に薙ぎ倒されて、炎はすでに欠片も見当たらなかった。水で濡れた小さな
小動物が、身体を小刻みに震わせながらそこから出てくるのをオスカーは静かに待っ
た。
一見してウサギのような動物だった。赤く透き通った瞳と、白い滑らかな毛皮。そ
して長く伸びた耳は今は怯えのためか、背中の方へと垂れ下がっている。
とある惑星で生息する特殊能力を有する生命体だった。彼らは思考したことを具現
化する能力を持っている。炎を思えばそこに炎が、水を思えばそこに水が出現するの
だ。
「よお、お嬢ちゃん。よく頑張ったな」
メスの性質を持つそれは、オスカーの言葉に嬉しそうに耳を動かすと、伸ばした手
に飛び込んできたのだった。
天を仰いでいたアンジェリークの足元から立ち昇る光が、ゆっくりと消失してい
く。親友の傍らでサクリアの放出を見守っていたロザリアは、消失する光の行方によ
り、この事件が解決したことを知った。
アンジェリークの瞳が閉じられ、そしてもう一度開く。
「終わったの?」
「うん。もう大丈夫。やっぱりオスカーはすごいわ。あの子が怖くて泣いているだけ
だってこと、ちゃんと分かっていたのね」
「……そうかもね」
ロザリアの答えは苦笑に満ちている。彼女にしてみればオスカーの「大丈夫」とい
う立った一言で事態を悟り、自分が何をするべきなのかを判別した親友の能力こそ賞
賛すべきことだと思ったが、あえて口にはしなかった。
恐らく、こういったことは誰とでも出来るものではないのだろう。女王と守護聖と
いう関係を超えて、互いを求め合った結果が、この言葉を交わさない『会話』に繋が
るのかもしれない。……羨ましいものだ。
(わたくし、いつまでたってもオスカーには勝てないのね……)
それを寂しいとは思わない。むしろ唯一のライバルである彼が強ければ強いほど、
ロザリアとしても容赦をする必要がないから、むしろ妙な罪悪感を抱かなくてすむ。
「どうしますか、陛下。王立研究院へ向かいますか?」
「ええ! オスカーにお帰りなさいを言わなくちゃ。あと、救急箱」
「救急箱?」
そんなものが何故必要なのか。むしろ救急箱よりも病院に連れていった方が早いの
ではないだろうか。
言葉にしないロザリアの疑問に、アンジェリークはスカートの裾を裁きながら笑っ
た。
「だってオスカー、掌を火傷してるんだもの。病院で手当てするまで冷やしてあげれ
ばそんなに痛みも続かないでしょ?」
オスカーは改めて火傷をした掌を見つめた。彼女が心配そうに耳を揺らして、舌で
傷を舐めてくる。
オスカーは彼女の頭を撫でてやると、右肩に彼女を乗せた。
「大丈夫だ。すぐに俺のお嬢ちゃんが救急箱を持ってくるぜ」
《ナゼ・ワカルノ》
オスカーは氷蒼の瞳を細める。
「……さあ、なんでだろうな」
ちゃんとした答えが貰えないことが不満だったのか、彼女は長い耳でオスカーの頭
を軽くはたいた。